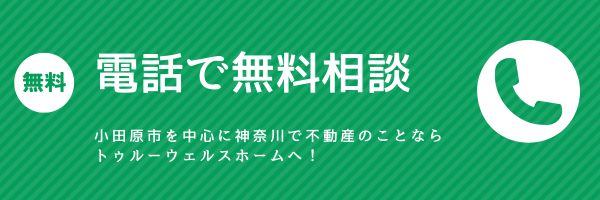相続した家の固定資産税の計算や納付は、不動産を所有する上で避けて通れない重要な手続きです。
特に相続直後は、登記や相続税の申告といった多くの事務処理に追われるため、固定資産税について後回しにしてしまうケースも少なくありません。
しかし、納付を怠ると延滞金が発生し、最悪の場合は財産の差押えにつながることもあります。
ここでは、相続した家の固定資産税について、誰がいつまでに支払うのか、計算方法、そして活用できる軽減措置までを詳しく解説し、スムーズな不動産管理に役立つ情報を整理しました。
固定資産税は誰がいつ払うのか?
納税義務者の決定
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点での不動産所有者です。年の途中で相続が発生した場合、その年の納税義務は亡くなった方(被相続人)にありますが、その義務は相続人に引き継がれます。
翌年からは、1月1日時点で法務局に所有者として登記されている人が新たな納税義務者となります。
相続登記が済んでいない場合の対応
相続が発生しても、すぐに遺産分割協議や相続登記が完了しないケースは多いです。
その場合、自治体は「相続人代表者指定届」の提出を求めることが一般的です。
この届出を提出することで、納税通知書を代表者が受け取り、支払いをスムーズに行うことができます。
もし届出がない場合、自治体が代表者を指定することもあります。
相続した家の固定資産税の計算方法
評価額の確認手順
固定資産税の計算は、まず相続した不動産の「固定資産税評価額」を確認することから始まります。
この評価額は、毎年4月〜6月頃に市区町村から送られてくる納税通知書に添付の「課税明細書」で確認するのが最も簡単です。
また、市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取得することでも確認できます。
計算の基本と税率
固定資産税は、以下の計算式で算出されます。
課税標準額 × 税率(標準は1.4%)
「課税標準額」は、原則として固定資産税評価額と同じですが、後述する軽減措置が適用される場合は評価額よりも低くなります。
税率は全国的に1.4%が標準ですが、自治体によっては異なる場合があります。
また、市街化区域内にある場合は、都市計画税(上限0.3%)が別途課されることもあります。
計算例を参考に理解を深める
例えば、土地の評価額が2,000万円、建物の評価額が500万円の家を相続したとします。
土地が200㎡以下の小規模住宅用地であれば、「住宅用地の特例」により課税標準額は評価額の1/6(約333万円)に軽減されます。
この場合、年間の固定資産税は「(土地の課税標準額333万円 + 建物の評価額500万円)× 1.4% = 約11.6万円」となります。
このように、軽減措置の適用有無で税額は大きく変わります。
固定資産税の納付について
納税の期限とスケジュール
固定資産税の納付は通常、年4回に分けて行います。
多くの自治体では、6月、9月、12月、翌年2月といった期日が設定されていますが、地域によってスケジュールは異なるため、送付される納税通知書で必ず確認しましょう。
もちろん、第1期の納期限までに全額を一度に支払うことも可能です。
納付方法と便利な支払い手段
従来は役所や金融機関の窓口払いが一般的でしたが、現在ではコンビニ払いや口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなど多様な納付方法が用意されています。
口座振替を設定しておけば納付忘れを防げるため安心です。
利用できる支払い方法は自治体によって異なるため、納税通知書や自治体のウェブサイトで確認しましょう。
遅延した場合のペナルティ
万が一納付が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が課されます。
延滞金は未納額と経過日数に応じて計算されるため、遅れるほど負担が増加します。
納税を長期間怠ると、預金や不動産などの財産が差し押さえられることもあるため、必ず期限内に納税しましょう。

相続した家に適用される固定資産税の軽減措置
住宅用地の特例
相続した家に適用される最も代表的な軽減措置が「住宅用地の特例」です。
これは、人が住むための家屋の敷地(住宅用地)に対して課税標準額を大幅に引き下げる制度です。
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準額が評価額の6分の1
・一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準額が評価額の3分の1
被相続人が居住していた家を相続し、引き続き住宅として利用する場合、この特例は継続して適用されます。
その他の軽減措置
もし相続した家が新築から間もない場合、「新築住宅の減額措置」が適用されている可能性があります。
これは新築後一定期間(一般住宅は3年間)、家屋の固定資産税が2分の1に減額される制度です。
相続によって所有者が変わっても、期間内であれば減額は継続されます。
まとめ
相続した家の固定資産税は、まず誰が納税義務者になるかを把握し、納税通知書で評価額や税額を確認することが第一歩です。
その上で、住宅用地の特例などが正しく適用されているかを確認し、期限内に納付する必要があります。
相続直後は手続きが多く大変ですが、税金のことを後回しにせず、早めに確認・準備を進めることで、不要な延滞金やリスクを避けることができます。
もし不明な点があれば、不動産を管轄する市区町村の税務課や、税理士などの専門家へ相談することも有効な手段です。